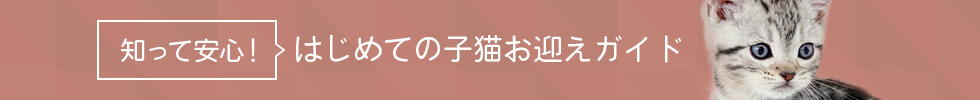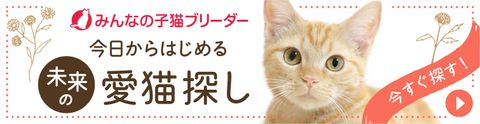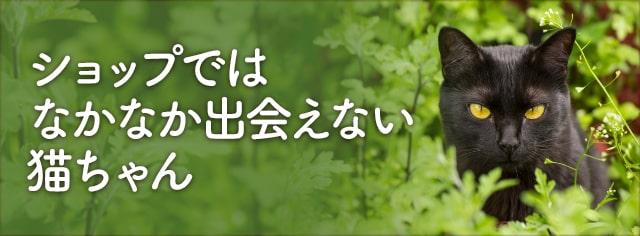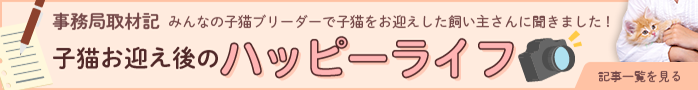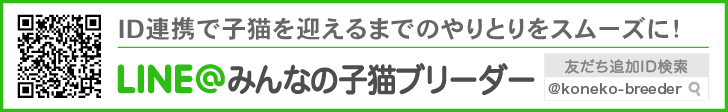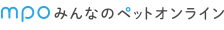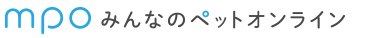子猫の夜鳴きの原因と対策

子猫の夜鳴きは、お迎え後1週間〜10日ほど続くことが多く、慣れない環境に対する自然な反応といえます。
ただし、そのまま放置してしまうと、不安を増幅させたり、ストレス要因になる可能性も。夜鳴きがはじまったら、まずは原因を見極めて、子猫に合った対応をとることが大切です。
ただし、そのまま放置してしまうと、不安を増幅させたり、ストレス要因になる可能性も。夜鳴きがはじまったら、まずは原因を見極めて、子猫に合った対応をとることが大切です。
環境変化による不安
母猫や兄弟と離れた子猫は、急にひとりになることで強い不安や寂しさを感じやすくなります。とくに月齢の低い子猫は、夜ひとりになる不安から夜鳴きしやすい傾向があります。
また、新しい匂いや音、照明、寝床などに馴染めず落ち着かない場合も、夜鳴きにつながります。
また、新しい匂いや音、照明、寝床などに馴染めず落ち着かない場合も、夜鳴きにつながります。
対策
- 安心できる環境づくり 飼い主の寝室近くにケージを置いておく、タオルなど母猫の匂いに似たアイテムを寝床に入れるのも効果的です。
- 暗くて静かな空間をつくる 音や光が強すぎると眠りの妨げになることもあります。照明をなるべく暗めにするのもポイント。
- 日中の過ごし方を工夫する
空腹やトイレのサイン
子猫が夜中に鳴く原因の一つが、空腹やトイレの不快感です。
とくにお迎え直後の時期は、食事や排泄のタイミングが安定しておらず、「おなかがすいた」「トイレが汚れている」といった生理的な不快を鳴いて訴えることがあります。
「夜鳴き=甘え」と決めつけず、まずは空腹や排泄が原因でないかを確認することが大切です。
とくにお迎え直後の時期は、食事や排泄のタイミングが安定しておらず、「おなかがすいた」「トイレが汚れている」といった生理的な不快を鳴いて訴えることがあります。
「夜鳴き=甘え」と決めつけず、まずは空腹や排泄が原因でないかを確認することが大切です。
予防・対策
- 寝る前の食事タイミングを調整する 夜間の空腹を避けるため、就寝前に軽く食事を与えると夜鳴きが減ることがあります。
- 清潔なトイレ環境を保つ 排泄物の残りや嫌なニオイがストレスになることも。寝る前にトイレの掃除をし、快適な状態を保ちましょう。
成猫の夜鳴きの原因と対策

発情期の影響
避妊・去勢手術をしていない成猫に多く見られるのが、発情期による夜鳴きです。
発情期の猫は、異性を求める本能によって大きな声で鳴いたり、外に出たがるような行動をとることがあります。夜間は静かなため、猫の鳴き声がより目立ち、「夜鳴きがひどい」と感じる飼い主さんも少なくありません。
この夜鳴きは猫にとって自然な行動ではありますが、本人も強いストレスを感じている状態でもあるため、早めの対処が望ましいでしょう。
発情期の猫は、異性を求める本能によって大きな声で鳴いたり、外に出たがるような行動をとることがあります。夜間は静かなため、猫の鳴き声がより目立ち、「夜鳴きがひどい」と感じる飼い主さんも少なくありません。
この夜鳴きは猫にとって自然な行動ではありますが、本人も強いストレスを感じている状態でもあるため、早めの対処が望ましいでしょう。
予防・対策
- 避妊・去勢手術を検討する 手術によって発情期の夜鳴きが軽減されるケースが多く、ストレス緩和にもつながります。
- 発情期のサインを見逃さない 落ち着きがなくなる、スリスリ行動が増える、排尿の回数が増えるなどのサインが見られたら、発情期に入った可能性を考慮しましょう。
- 外からの刺激を減らす
甘え、構ってほしい気持ち
猫は基本的にマイペースと思われがちですが、なかには飼い主に強く甘える性格の子もいます。「もっと構って」「そばにいて」という気持ちから夜に鳴くこともあります。
昼間にあまり遊んでもらえていない、スキンシップが不足していると感じると、夜になってから構ってアピールとして鳴くケースが増えます。
「鳴けば飼い主が来てくれる」と学習してしまうと、夜鳴きが習慣になることもあるため注意が必要です。
昼間にあまり遊んでもらえていない、スキンシップが不足していると感じると、夜になってから構ってアピールとして鳴くケースが増えます。
「鳴けば飼い主が来てくれる」と学習してしまうと、夜鳴きが習慣になることもあるため注意が必要です。
予防・対策
- 日中にしっかり遊ぶ時間をとる 日中に運動不足だと夜に元気になる傾向があります。お気に入りのおもちゃを使って遊ぶことで、心も体も満たされて夜は穏やかに過ごせるようになります。
- 就寝前のスキンシップを習慣にする 寝る前に撫でたり、優しく声をかけたりすることで、猫に安心感を与えることができます。日々のスキンシップが信頼関係を深め、夜鳴きの予防にもつながります。
- 鳴いてもすぐに反応しすぎない
生活リズムのズレ
猫が夜に活発になるのは「薄明薄暮性」であるためです。飼い主との生活リズムが合わないと、夜に活発になりすぎてしまうことも……。
昼間に寝てばかりの猫は、夜にエネルギーを発散しようとして活発になります。これが「夜鳴き」や「夜の運動会」の原因になることもあります。
昼間に寝てばかりの猫は、夜にエネルギーを発散しようとして活発になります。これが「夜鳴き」や「夜の運動会」の原因になることもあります。
予防・対策
- 昼間の活動量を増やす工夫をする 帰宅後や日中の在宅時間にたっぷり遊んであげて、夜には満足して眠れるようにしましょう。寝る前の運動+スキンシップの時間を習慣にすると、猫のリズムも少しずつ整っていきます。
- 就寝時間をある程度固定する 毎日バラバラな就寝スケジュールだと猫も混乱します。生活リズムを安定させることが、夜鳴き対策につながります。
猫は夜行性じゃなかった? 猫が夜活動する理由と対策
猫が夜行性と勘違いされる原因や、実際の生活スタイルについて説明します。また、「猫が夜に暴れて困っている」飼い主さんに向けて、対処方法もご紹介します。
シニア猫の夜鳴きの原因と対策

認知機能の衰え(猫の認知症)
シニア猫が夜中に理由もなく鳴き続ける場合、「認知機能の低下(いわゆる猫の認知症)」が原因の可能性があります。
高齢になると、昼夜の区別がつきにくくなり、トイレの場所や生活パターンがわからなくなることも。結果として夜間に混乱して鳴き出す、同じ場所をうろうろするなどの行動が見られます。
このような夜鳴きには、猫自身も不安や混乱を感じているため、落ち着ける環境づくりや生活サポートが重要です。
高齢になると、昼夜の区別がつきにくくなり、トイレの場所や生活パターンがわからなくなることも。結果として夜間に混乱して鳴き出す、同じ場所をうろうろするなどの行動が見られます。
このような夜鳴きには、猫自身も不安や混乱を感じているため、落ち着ける環境づくりや生活サポートが重要です。
予防・対策
- 環境の変化を最小限にする 家具の配置や生活動線を極力変えないようにし、猫が混乱しないよう配慮しましょう。
- 夜間でも安心できる照明を 完全な暗闇だと不安が強まることもあります。豆電球や足元灯をつけておくことで落ち着くことがあります。
- 日中の刺激とスキンシップ 昼間に軽く遊んだり声をかけたりして、適度な刺激と安心感を与えることも、夜の混乱を軽減するのに役立ちます。
痛みや体の不調
シニア猫が夜に落ち着かず鳴くのは、痛みや不調が原因の可能性があります。
関節炎や歯の痛み、内臓の病気など、加齢による慢性的な不快感が夜鳴きにつながるケースは少なくありません。夜間は人目が届かず不安も強まりやすいため、注意が必要です。
関節炎や歯の痛み、内臓の病気など、加齢による慢性的な不快感が夜鳴きにつながるケースは少なくありません。夜間は人目が届かず不安も強まりやすいため、注意が必要です。
予防・対策
- 普段と違う行動がないか観察する トイレの回数が増えた、食欲がない、歩き方がぎこちないなど、小さな変化も見逃さずチェックしましょう。
- 早めに動物病院を受診する 痛みや病気による夜鳴きは、早期に診断・治療することが何より大切です。高齢猫は些細な変化が深刻な症状につながることもあります。
- 寝床の環境を整える 関節や筋肉の負担を軽減するために、柔らかく暖かいベッドやクッションを用意してあげると安心して休みやすくなります。
視覚・聴覚の衰えによる不安
視力や聴力が衰えたシニア猫は、環境を把握しにくくなり、不安から夜鳴きをすることがあります。
とくに暗い部屋では視界が効きづらくなり、どこにいるか分からなくなってパニック状態に陥ることも。聴覚の衰えにより生活音や飼い主の声が聞こえにくくなり、「ひとりぼっちになった」と感じて鳴いてしまうケースも見られます。
夜間に猫が落ち着きなく歩き回る、飼い主の声に反応しないなどの様子が見られる場合は、感覚機能の衰えが原因かもしれません。
とくに暗い部屋では視界が効きづらくなり、どこにいるか分からなくなってパニック状態に陥ることも。聴覚の衰えにより生活音や飼い主の声が聞こえにくくなり、「ひとりぼっちになった」と感じて鳴いてしまうケースも見られます。
夜間に猫が落ち着きなく歩き回る、飼い主の声に反応しないなどの様子が見られる場合は、感覚機能の衰えが原因かもしれません。
予防・対策
- 夜間の不安を和らげる照明に 夜間でも猫が安心して移動できるよう、常夜灯や足元灯をつけるなど明るさの工夫をしましょう。
- 家具の配置を固定する 視覚が弱っても慣れた動線を頼りに行動できるよう、レイアウトはできるだけ固定しておくことが大切です。
- 優しく声をかけて存在を伝える 飼い主の声は、安心感につながります。無理に抱っこせず、近くに寄って声をかけるだけでも落ち着く猫は多いです。
猫の夜鳴きの対処法でやってはいけないこと

1. 怒鳴る・叱る・大きな音で威嚇する
猫は怒鳴られても理由が分からず、恐怖やストレスを感じるだけです。大声や物音で黙らせようとすると、安心感が損なわれ、夜鳴きがかえってひどくなることもあります。
2. 毎回構ってあげる
夜鳴くたびに構っていると、「鳴けば構ってもらえる」と学習し、夜鳴きが習慣化してしまいます。とくに甘え鳴きタイプの猫には逆効果となる場合があるため、冷静な対応が必要です。
3. 完全な無視を続ける
「無視すればやめる」とされることもありますが、子猫や不安を抱えている猫の場合は逆効果です。原因が空腹やトイレ、体調不良によるものだった場合、無視してしまうことで体調悪化につながることも。
4. 生活リズムを大きく変えてしまう
「夜鳴きを避けるために猫の生活リズムを急に変える」といった対応も、猫にとっては混乱のもと。できるだけ一貫性のある生活環境を維持しながら、徐々に改善を図ることがポイントです。
関連する記事
まとめ

猫の夜鳴きには、環境への不安、空腹、発情、加齢などさまざまな原因があります。子猫・成猫・シニア猫それぞれに適した対策をおこなうことが大切です。「無視していいの?」「いつまで続くの?」といった疑問を感じたら、まずは原因を見極めましょう。
誤った対応は逆効果になることもあるため注意が必要です。夜鳴きの背景を理解し、猫との暮らしをより快適に整えていきましょう。
関連する記事
誤った対応は逆効果になることもあるため注意が必要です。夜鳴きの背景を理解し、猫との暮らしをより快適に整えていきましょう。